ヒュー ジョンソン 著『ワイン物語―芳醇な味と香りの世界史〈下〉』
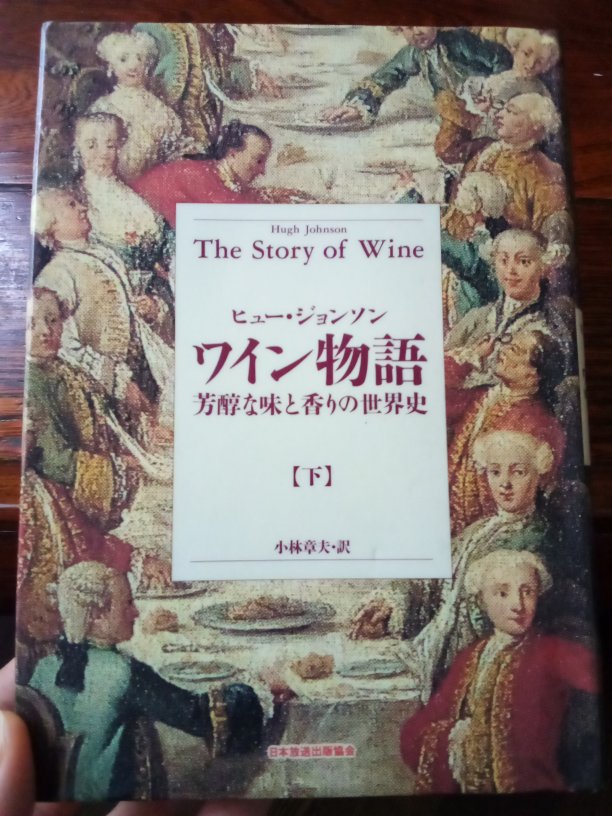
2022/6/14






一読済。英国ワイン評論家である著者が執筆した “ワインの文化史”。下巻は中世~現代にかけて纏められている。著者が1540年産のワインを試飲した感想が書かれており、本書通じて大変興味深く勉強になった???
以下参考・抜粋:
マデイラ・ワイン – Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%87%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%83%BB%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3
「マデイラ」ってどんなお酒? | エノテカ – ワインの読み物
https://www.enoteca.co.jp/article/archives/16750/
P.109-110
シェイクスピアより古いワイン。いったいどんな味がするのだろうか。試飲するのは私を含めて数人だったが、実のところ、みんなそれほど期待していなかった。(中略)
だが、一五四〇年産のシュタイン・ワインは生きていた。私はこのときほど強く、ワインは生き物だと感じたことはない。この褐色の、マデイラ・ワインに似た液体は、遠く過ぎ去った夏の太陽が宿した生命の本質を、今なお内にに秘めていたのだ。言葉にするのは難しいが、そのワインのふるさと、ドイツを思わせる何かが感じられた。だが、二口ばかりも飲んだ頃には、残念ながらこの四世紀を生き抜いたワインは、空気に触れたのが原因で駄目になってしまった。味を支える生命が昇天してしまったとでもいうべきか。グラスの中で酢と化してしまったのだった。
このような年代物を飲むのは、どんな場合でも心躍る出来事に違いない。だが、このワインの味がひときわ感動的だったのは、それによってドイツ・ワインの黄金期の味を体験できたからである。十六世紀の初頭は、ドイツが、北ヨーロッパのワイン産地として、量的にも質的にも頂点を極めた時期であった。
ヴュルツブルクシュタイン
https://fuguja.com/wc3bcrzburger_stein
シェリー酒ってどんなお酒? | エノテカ – ワインの読み物
https://www.enoteca.co.jp/article/archives/9610/
フィロキセラとは?ワインを襲う害虫とその対策 | アカデミー・デュ・ヴァン ブログ
https://www.adv.gr.jp/blog/phylloxera/
世界中のブドウを襲った害虫「フィロキセラ」とは? | エノテカ – ワインの読み物
https://www.enoteca.co.jp/article/archives/5965/
ワイン造りの一大革命を起こした!!ワインとルイ・パスツール |
香りと記憶がテーマのWEBメディアLoin(ロワン)
https://loin-vin.jp/post/1629
「うどんこ病」を詳しく解説 – ワインリンク
https://wine-link.net/pc/dictionary/detail/1570
P.431
ワインの本質である品質とはまったく別の、歴史、本物であること、稀少性。「本場」であるといったことが全て有利に働き、フランスの一級品の値段は常にトップの座を保ってきた。
P.438
忘れてはならないのは、ワインは自然界の奇跡の一つで、人間と一万年もつきあっていながら、いまだ未知の要素をもち、またあらゆる食物の中でワインだけが自立した生命をもっているからこそ、人間はこれを神聖視するという点なのである。
農民も芸術家も、勤勉家も夢想家も、快楽主義者もマゾヒストも、錬金術師も会計士も——こういったすべての人々がワインを育てるのである。ノアの洪水以来、ずっとそうだったのだ。
ヒュー ジョンソン 著『ワイン物語―芳醇な味と香りの世界史〈下〉』https://amzn.to/3Hm4ivN
https://twitter.com/akashi_takuya/status/1536591543523774465
http://lovefami.s1008.xrea.com/wp/?p=10945

