坂口 謹一郎 著『坂口謹一郎酒学集成〈4〉酒中つれづれ』
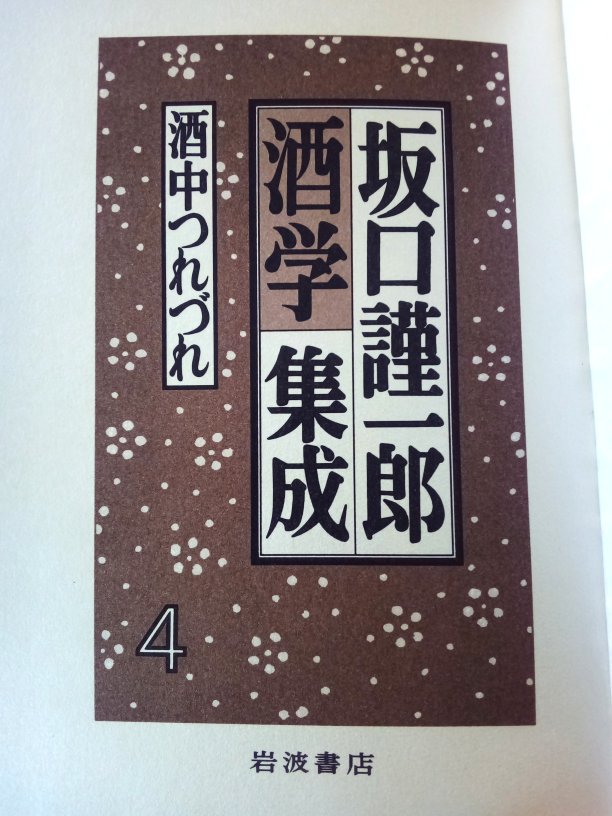
2022/12/22






読了。発酵醸造学の権威である著者が各誌に寄稿した文章・講演録・エッセイ等が収録。日経新聞 “私の履歴書”、酒/発酵学、日常生活等、著者の深い知識造詣と酒造業界の歴史が読み取れ、大変興味深く読ませて頂いた🙏😌🍶
P.218
酒は人の飲食の中での最高の芸術品である。
P.219
一昨年(一九七〇)の春、長野県佐久市の大沢さんという酒屋さんが、約三〇〇年前の元禄二年に実家の創業時代の酒を封じたものであるといってそれを持参された。
【信州・佐久の地で元禄2年に創業した、清酒「明鏡止水」大澤酒造】
P.220
酒屋万流
酒蔵萬流 | 酒蔵萬流
酒屋万流!日本酒の歴史を支えてきた三大杜氏集団とは? | 日本酒専門WEBメディア「SAKETIMES」
P.229
「泡はビールなりや否や」事件
「ビールの泡はビールか!?」 裁判の判決は・・・ | 広島を生ビールで元気にしたい!ひろしま元気プロジェクト
かけ出し裁判官Nonの裁判取説:「泡はビールなりや否や」事件
P.287
余計な心の働きに支配されずにお互いお茶を飲み、お菓子を食べ、杯を交わし、ああこれはうまいなとかまずいなどといって愉快に生きている姿が、その道なのではないだろうか。
P.288
人と人が、ある食べ物を媒介として、それは酒であれ、お茶であれ、コーヒーであれ、なんでもよいのだが、お互いに「和をもって貴しとなす」とした精神で交流することが大切なのである。そのことが酒道の精神であり、茶道の精神であると私は考える。
P.300
酒質の調和だけは、日本酒に限らず世界中の酒を通じての、大切な基本的性格であるということである。これを解り易く表現すれば、『さわりなく水の如くに飲める』ということである。うちに千万無量の複雑性を蔵しながら、さりげない姿こそ酒の無上の美徳であろう」と書かれている。
この数年来の吟醸酒の登場も含めて、「さわりなく水の如くに」飲める酒が歓迎されるようになってきたことや、さまざまに個性的な、地方の酒が競い合っている状況をみれば、この坂口先生の提言が受け入れられてきたことの証であろう。
P.316
先生は、人生の無常感や微生物を含めての生命観を、何としても表現しないではいられなかった方で、それが、多くの歌になったものと思われる。さきにあげた「一期一会」の歌もそうだが 例えば、
めにみえぬちひさきもののちからもて これのうまさけかもすかみわざ
わがいのちふと惜しまれぬ山の端を はなるる月のあまり速きに
宗教的人間という存在は、生死についての感受性が、人一倍つよいところが苦しいのであるが、後進を励ます歌や祝ぎ歌の基底にも、「人皆よく生きよ」という先生の願望と思想があらわれている。
P.317
もう三十年以上もむかしのことになる。当時、私の友人から、「坂口の前に坂口なく、坂口の後に坂口なし」といわれたことがある。おそらく一高入学時の秀才ぶりについての評判なのであろう。坂口先生のように、豊かな教養と学問的な基礎の上に「酒学」を論じ、しかも品格のある方にはもうお会いすることができない、という感慨とともに、この言葉を思い出すのである……。
坂口 謹一郎 著『坂口謹一郎酒学集成〈4〉酒中つれづれ』https://amzn.to/3VjS2kZ
https://twitter.com/akashi_takuya/status/1605809448605274115
http://lovefami.s1008.xrea.com/wp/?p=13018
http://lovefami.s1008.xrea.com/wp/?p=10317
http://lovefami.s1008.xrea.com/wp/?p=9789
http://lovefami.s1008.xrea.com/wp/?p=7339
http://lovefami.s1008.xrea.com/wp/?p=10165
http://lovefami.s1008.xrea.com/wp/?p=8681
http://lovefami.s1008.xrea.com/wp/?p=6568

