鮫島 吉廣 著『焼酎 一酔千楽』
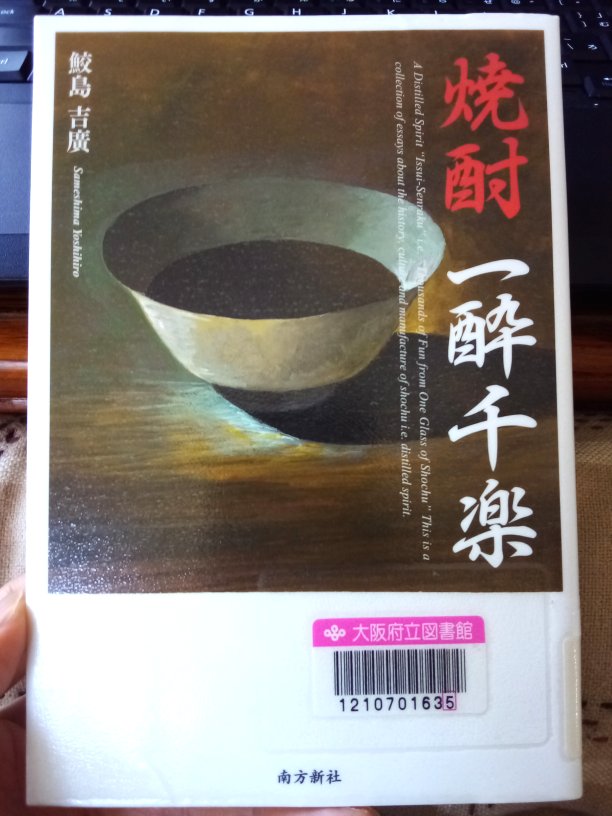
2022/3/13






読了。薩摩酒造研究所長兼製造部長/鹿児島大学で焼酎の製造技術を教える著者が執筆する “焼酎” に纏わるエッセイ集。著者の焼酎愛&焼酎に対する豊富な知識/見識が読み取れ大変勉強になった。私も “薩摩焼の黒じょか” を手に入れ愉しみたい???
P.15
「憂さを忘れて飲もうじゃないか。なぁ、我が友よ。まずは乾杯、人生に」。
P.36
人はなぜ酒を飲むのかという問いに「自分以外の存在になりたいから」と喝破したのは作家の開高健である。なるほどと思う。自分の家で飲む酒もいいが、たまには太陽の下で飲んでみたい。焼酎には太陽がよく似合う。
P.96
「美」とは時代を超えて光り輝くものである。いたずらに旧慣を墨守するのではなく、時代に磨かれ光芒を放つものをいう。地下の穴蔵に蓄えられ泥で密封された中から掘り出された白酒のモロミは蒸留されて、強烈な香気を放つ酒へと生まれ変わる。醜いアヒルが白鳥へ変身するような劇的な変貌である。そこには発酵と蒸留の絶妙な調和の世界があり、酒造りの常識を覆し、人知を超えた「美」がある。時代に迎合しないその酒は、海の青、空の青にも染まず漂う白鳥の美しさにも似ている。
P.116
思えば、酒の中にはその土地柄がぎっしりと詰め込まれている。凍てつく冬の寒さの中で清酒造りは磨かれてきた。焼酎杜氏がみればこんなところで焼酎は造りたくないと思うだろう。芋焼酎は室温が三〇度を超える暑い季節に汗だくになりながら造られる。清酒杜氏はこれは酒を造れる環境ではない、と思うだろう。だが、どちらも心身ともに温めてくれる味を目指すのは同じである。
P.133
江戸時代につくられた「酒の十徳」には次のような項目が挙げられている。①独居の友、②労をいとい、③憂いを払う、④病をさけ、⑤毒を消し、⑥寒気の衣となる、⑦万人和合す、⑧位なくして貴人と交わる、⑨縁を結び、⑩人寿を延ぶ。
P.186
席に着くや、早速燗酒一本注文した。しばらくするとお店の人が玉手箱のような朱塗りの箱をもってきて、五分間おまちください、と言う。酒を注文して箱が出てくるのは初めての経験である。箱を開けてみて唸った。箱の上蓋をとると、内側にはあざやかな朱の漆が塗られている。蓋のないものはあるようだが蓋つきは見たことがなかった。蓋をあける前の玉手箱気分がなんともいえない。シンプルな中に気品が漂っている。箱の中にはお湯が入っていて、そこに酒の入った徳利が浸かっている。徳利に合わせた箱の大きさなので徳利が倒れることはない。五分間待つとちょうど手ごろの温度になる。ぬるくなれば、箱の湯に浸ければよい。はやる気持ちを抑えて待たせる五分間の演出も心にくい。
P.198-199
酒に酒器はつきものだが、黒ジョカと芋焼酎ほど相性のいい取り合わせはない。(中略)つまり、黒ジョカは水で割った芋焼酎を直火で温めるものなのである。
そして、黒ジョカと蒸留酒である芋焼酎は酒器と酒という関係に加えて、土のにおい、風土のかおり、火から生まれる共通の素朴さとバイタリティーを持ち、それが互いの絆を一層深めているように思える。黒ジョカで飲む焼酎は、火から生まれた酒器と焼酎がまた火でひとつに結ばれることを意味する。使えば使うほど味が染み出て、いぶし銀のような古武士を思わせる風格が出てくるところは実に薩摩的である。
P.230
紆余曲折のつもりが、気が付いてみれば焼酎一直線の人生となっていた。焼酎の取り持つ縁が思いもかけない方向へと導いてくれた。酒に酔い人に酔い、まさに一酔千楽の世界を歩んできたように思う。
鮫島 吉廣 著『焼酎 一酔千楽』https://amzn.to/3tN9pyS
https://twitter.com/akashi_takuya/status/1502819810044162049
https://twitter.com/akashi_takuya/status/1503007984137515013
2022/2/20
https://twitter.com/akashi_takuya/status/1495231746786299905
https://twitter.com/akashi_takuya/status/1495233585963577344
2022/2/10
https://twitter.com/akashi_takuya/status/1491643319759564800
https://twitter.com/akashi_takuya/status/1491642348694302722
- タグ:
- 書籍

